07-g-24
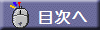
[季節] 晩夏を主に三夏(7月を主に5月から7月)植物季題
[季題] 半夏生草(はんげしやう/はんげしょう)
[副題] 片白草(かたしろぐさ)
半夏草(はんげぐさ)
水辺に白い根茎を伸ばして群生する高さ50〜100cmの多年草。
葉は長卵形で茎頂に7月初旬ころに小さな黄白色の花を穂状に多数つける。
名の由来は半夏生のころに花をつけるからとも或いは葉の下半分が白くなりその白い部分を半分化粧した姿に譬えたともいわれている。
俳句では七十二候の一つの季題「半夏生」と混同しないように植物の半夏生は「草」を添え「半夏生草」と表記して「はんげしょう」と5音で読みならわせられている。
木村宏一氏 撮影

クリックすると写真が拡大します。
←
半夏生の俳句 清月俳句歳時記7月の俳句、植物俳句のページです。例句は、インターネット俳句清月俳句会の投句及び廃刊俳誌「引鶴」の雑詠句或いは芭蕉俳句などから有季定型俳句・伝統俳句作品を抽出しています。京都清月庵 木津川市 大阪清月庵 枚方市。編者野田ゆたかは、平成22年1月現在、ホトトギスに投句し指導を仰ぐとともにインターネット俳句「清月」を主宰しています。 [季節] 晩夏を主に三夏(7月を主に5月から7月) 植物季題/[季題] 半夏生草(はんげしやう/はんげしょう)/[副題] 片白草(かたしろぐさ) 半夏生草(はんげしやうぐさ/はんげしょうぐさ)/水辺に白い根茎を伸ばして群生するち高さ50〜100センチの多年草。/葉は長卵形で茎頂に7月初旬ころに小さな黄白色の花を穂状多数つける。/名の由来は半夏生のころに花をつけるからとも或いは葉の下半分が白くなりその白い部分を半分化粧した姿に譬えたともいわれている。/この季題は七十二候の一つの時候季題「半夏生」と同字・同音であるので花の状態・葉の状態・目にした場所などを添えて詠み植物であることがわかるように作句する必要がある。/俳人によっては「半夏生草」と表記して「はんげしょう」と5音で読ませる人もいる。/はんなりと片白草の林泉に揺れ 西村舟津の俳句/母の忌や片白草の浮き立ちて 吉野濃菊の俳句/雨上り化粧直して半夏生 木村宏一の俳句 /橋へだてここより寺領半夏生草 藤戸寿枝の俳句/白塗りの顔を隠した半夏生 志村万香の俳句/出迎は明るい黄花半夏生 野田ゆたかの俳句/『半夏生(草)の俳句』ページのアドレス ・半夏草の俳句半夏草折らむとすれば根が抜けて 舘野翔鶴